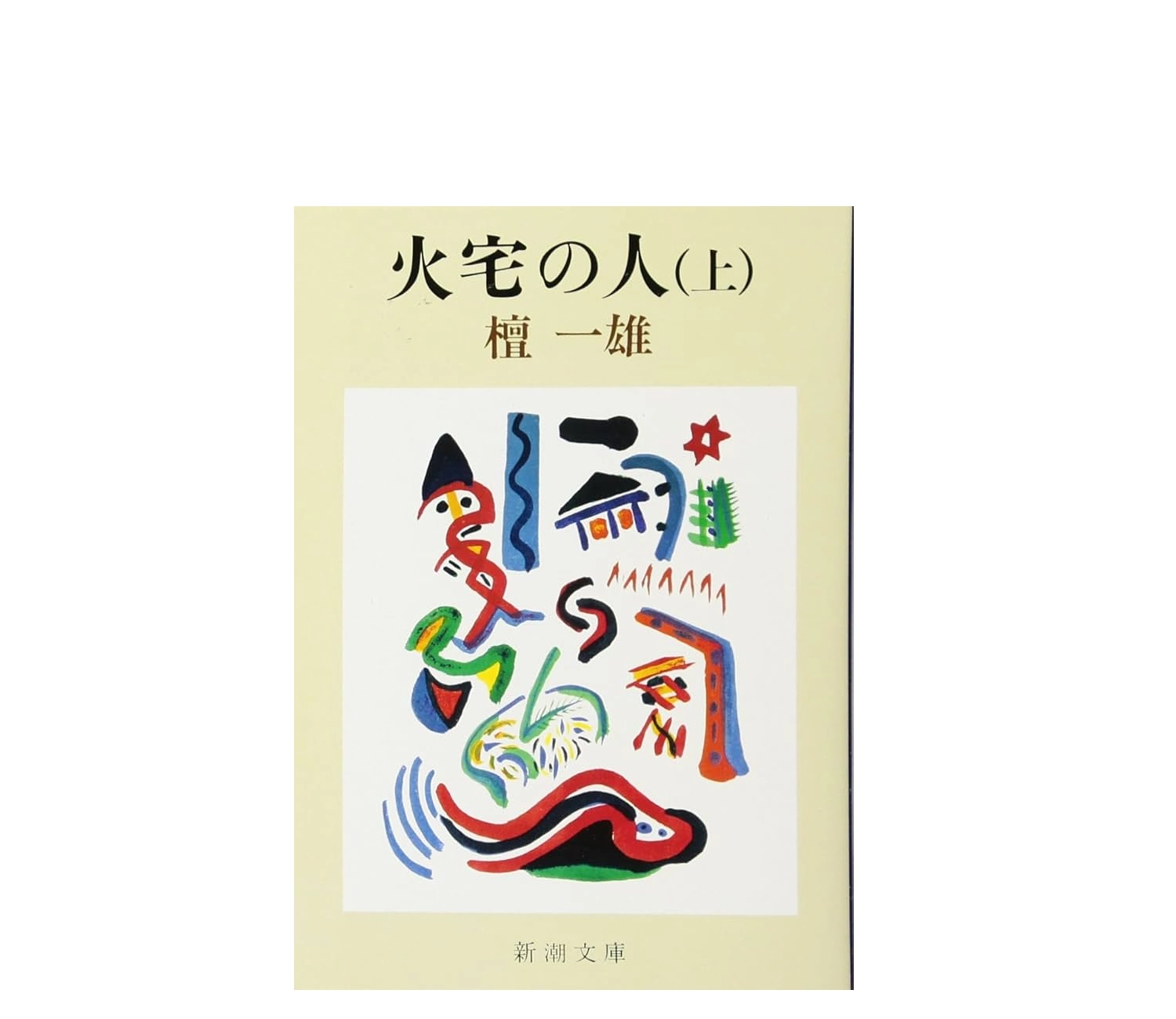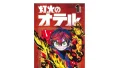檀一雄の遺作として知られる「火宅の人」について、小説のあらすじをお探しではありませんか。この記事では、この不朽の名作がどんな話なのか、そのあらすじはもちろん、主人公は誰で、どのような登場人物がいるのかを詳しく解説します。
また、火宅の人のモデルは誰なのか、物語は実話なのかという深い疑問や、タイトルの火宅の人とはどういう意味なのかにも迫ります。作者・檀一雄の人物像、映画やドラマのキャスト情報、そして多くの読者の心を揺さぶった読者の感想やレビューもあわせて紹介します。
最後に、この作品をどこで読めるのか、青空文庫で閲覧可能かといった実用的な情報まで、あなたの知りたいことを網羅してお届けします。
- 小説「火宅の人」の全体像とあらすじがわかる
- 作品の背景(モデルやタイトルの意味)を理解できる
- 登場人物や作者、映像化作品について詳しくなれる
- 読者の感想や作品を読む方法がわかる
小説「火宅の人」のあらすじを徹底解説

- 小説「火宅の人」はどんな話?あらすじ紹介
- 主人公は誰?主要な登場人物を紹介
- タイトル「火宅の人」とはどういう意味?
- 作者はどんな人?檀一雄について
- 20年にわたる長期連載の背景
小説「火宅の人」はどんな話?あらすじ紹介
檀一雄の『火宅の人』は、妻子を持ちながらも奔放な愛に生きる作家・桂一雄の破滅的でエネルギッシュな半生を描いた物語です。家庭と愛人との間で揺れ動き、苦悩しながらも自らの欲望に忠実に生きようとする主人公の姿を通して、人間の業や家族のあり方を深く問いかけます。
物語は、主人公である直木賞作家・桂一雄が、若い愛人・恵子と深い関係になるところから始まります。彼の家庭には、宗教に傾倒する妻・ヨリ子と、日本脳炎の後遺症で障害を負った次男・次郎を含む5人の子供たちがいます。一雄は家庭を顧みず恵子との生活を選びますが、その関係もまた嫉妬や喧嘩に明け暮れる不安定なものでした。
彼は家を飛び出し、日本各地を放浪する中で新たな女性・葉子と出会い、刹那的な日々を送ります。しかし、どこへ行っても家族への責任と罪悪感からは逃れられません。物語のクライマックスでは、次男・次郎の突然の死をきっかけに、一雄は再び家族のもとへと戻ることになります。崩壊したかに見えた家族が、悲劇を経て新たな関係を模索していくまでを描いた、壮絶な私小説です。
物語のポイント
家庭を捨てた作家が、愛人との破滅的な恋愛、全国放浪、そして息子の死を経て、再び家族と向き合うまでを描く、激しくも切ない一代記です。
主人公は誰?主要な登場人物を紹介

『火宅の人』には、主人公・桂一雄を取り巻く個性豊かな人物たちが登場します。それぞれの関係性を理解することで、物語をより深く楽しめます。
| 登場人物 | 概要 |
|---|---|
| 桂 一雄(かつら かずお) | 主人公の作家。檀一雄自身がモデル。家庭を顧みず、愛人である恵子や葉子との関係に溺れる。破天荒でありながらも、心の底では家族への愛情を捨てきれない複雑な人物。 |
| 桂 ヨリ子(かつら よりこ) | 一雄の妻。夫の奔放な生活に苦しみ、宗教に心の安らぎを求める。夫を突き放しながらも、子供たちのために家を守り続ける芯の強い女性。 |
| 矢島 恵子(やじま けいこ) | 一雄の若い愛人。女優の卵。一雄と激しい恋愛関係を結ぶが、その生活は嫉妬と喧嘩の絶えないものとなる。モデルは女優の入江杏子。 |
| 葉子(ようこ) | 一雄が放浪の旅の途中で出会う女性。複雑な過去を持ち、一雄と刹那的な関係を結ぶ。 |
| 桂 次郎(かつら じろう) | 一雄の次男。日本脳炎の後遺症で重い障害を負っている。彼の存在と突然の死が、物語の大きな転換点となる。 |
| 桂 一郎(かつら いちろう) | 一雄と先妻との間の長男。父の奔放な生き方に反発し、非行に走ることもある。 |
登場人物たちの複雑に絡み合う人間関係が、この物語の大きな魅力の一つです。特に、妻ヨリ子の静かな怒りと深い愛情、愛人恵子の激しい情念は、主人公の生き様をより一層際立たせています。
タイトル「火宅の人」とはどういう意味?

『火宅の人』という印象的なタイトルは、仏教の経典である法華経の「譬喩品(ひゆほん)」に出てくる言葉「火宅」に由来しています。
仏教における「火宅」とは、「燃え盛る家のように、多くの危うさと苦悩に満ちているにもかかわらず、本人はそれに気づかず遊びに夢中になっている状態」を指します。これは、煩悩や苦しみに満ちたこの世(現世)のたとえとして使われる言葉です。
この物語において、主人公の桂一雄はまさに「火宅」の中にいる人物として描かれています。家庭の崩壊、愛人との不安定な関係、子供の問題といった数々の苦悩に囲まれながら、彼は酒や女、旅に逃避し、その場限りの快楽を追い求めます。自らが燃え盛る家の中にいると知りながら、そこから逃れようとせず、あるいは逃れることができずに破滅的な生き方を続ける。「火宅の人」とは、まさにそんな主人公の生き様そのものを象徴したタイトルなのです。
豆知識:無頼派との関連
作者の檀一雄は、太宰治や坂口安吾らとともに「無頼派(ぶらいは)」の作家と称されました。既成の道徳に反発し、破滅的な生き様を作品に投影した彼らのスタイルは、「火宅」という言葉が持つ苦悩や危うさと深く通じるものがあります。
作者はどんな人?檀一雄について
『火宅の人』の作者である檀 一雄(だん かずお)は、1912年生まれの小説家で、「最後の無頼派」とも称される昭和文学を代表する作家の一人です。
福岡県柳川市の出身で、東京帝国大学在学中から執筆活動を開始。太宰治や坂口安吾といった作家たちと深く交流し、戦後の文壇で大きな存在感を示しました。自身の体験を色濃く反映した私小説を多く手がけ、中でも最初の妻・律子との死別を描いた『リツ子・その愛』『リツ子・その死』は高い評価を受けています。
豪快な人柄と料理へのこだわり
檀一雄は、作品だけでなく、その豪快で破天荒な人柄でも知られています。世界中を放浪する旅好きであった一方、文壇屈指の料理愛好家でもありました。彼の料理への情熱は『檀流クッキング』という著書にもまとめられており、今なお多くのファンに愛されています。
家庭を顧みない奔放な生き方は多くの人を振り回しましたが、その人間的な魅力やエネルギーが、彼の文学の源泉となっていたことは間違いありません。『火宅の人』は、そんな檀一雄の人生そのものを凝縮した、まさに集大成と呼ぶべき作品です。
20年にわたる長期連載の背景
『火宅の人』は、非常に長い年月をかけて執筆された作品です。最初の章である「誕生」が文芸誌『新潮』に発表されたのは1955年のことでした。
その後、約20年間にわたり、様々な雑誌で断続的に書き継がれていきました。これは、この物語が作者である檀一雄自身の人生と並行して進んでいたためです。彼の身に起こる出来事や心境の変化が、そのまま作品に反映されていきました。
執筆は決して順調ではなく、何度も中断されています。しかし、1975年に肺ガンで入院した檀は、病床で編集者の助けを借りて口述筆記という形で執筆を再開。命が燃え尽きる直前まで書き続け、最終章「キリギリス」を完成させました。
このようにして『火宅の人』は、作者の死と同時に完結した遺作となったのです。20年という歳月は、単なる執筆期間ではなく、作者が自らの人生を文学へと昇華させるために必要不可欠な時間だったと言えるでしょう。
「火宅の人」小説のあらすじ以外の魅力
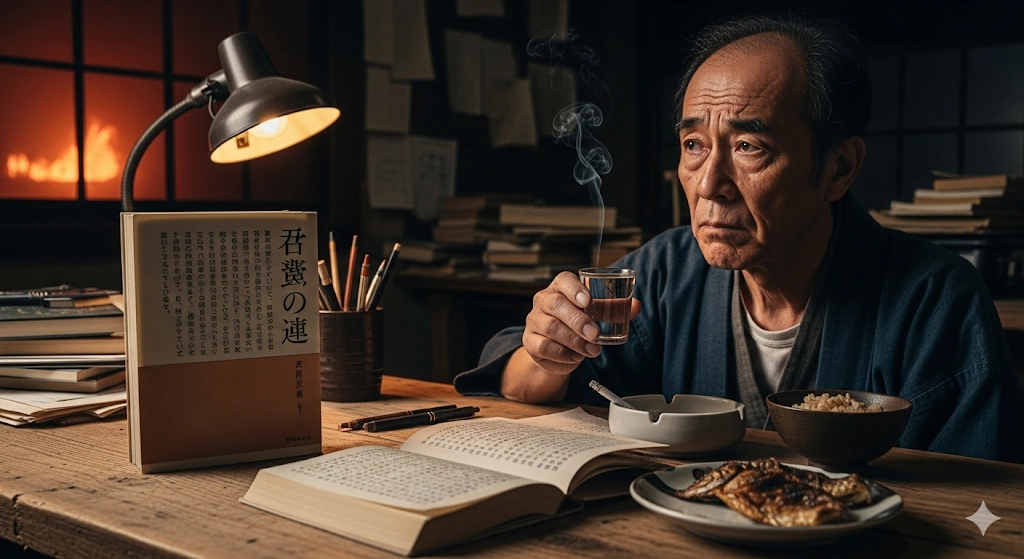
- 火宅の人のモデルは誰?実話なの?
- 作品が受賞した文学賞
- 映画やドラマのキャストは?
- 読者の感想やレビューを紹介
- どこで読める?青空文庫にある?
- 「火宅の人」小説のあらすじについて総括
火宅の人のモデルは誰?実話なの?
『火宅の人』は、作者自身の体験を基にした「私小説」として知られており、登場人物の多くに実在のモデルが存在します。
- 主人公・桂一雄:作者である檀一雄自身がモデルです。
- 愛人・矢島恵子:当時、檀一雄と恋愛関係にあった女優の入江杏子(いりえ きょうこ)がモデルとされています。
物語で描かれる出来事、例えば愛人との同棲や全国放浪、子供の病気などは、実際に檀一雄の身に起こったことがベースになっています。そのため、この作品は檀一雄の告白録や暴露本として読まれることも少なくありません。
注意:小説は「事実」そのものではない
前述の通り、物語の多くは事実に即していますが、完全にノンフィクションというわけではありません。作者の長男である檀太郎氏は「小説は小説、事実とは違います」と述べています。あくまで文学作品として、作者の心象風景や芸術的な脚色が加えられている点を理解しておくことが重要です。物語のリアリティを楽しみつつも、描かれていることが全て事実ではないという視点を持つと、より深く作品を味わうことができます。
作品が受賞した文学賞

『火宅の人』は、その文学的な価値が高く評価され、作者の死後に数々の権威ある文学賞を受賞しました。また、1986年に公開された映画版も、その年の映画賞を総なめにする快挙を成し遂げています。
小説の受賞歴
- 第27回 読売文学賞(小説部門)
- 第8回 日本文学大賞
これらの受賞は、檀一雄が生涯をかけて書き上げたこの作品が、日本文学史に残る不朽の名作であることを証明しています。
映画版の主な受賞歴
1986年に深作欣二監督、緒形拳主演で映画化された際にも、非常に高い評価を受けました。
| 受賞名 | 受賞内容 |
|---|---|
| 第10回 日本アカデミー賞 | 最優秀作品賞、最優秀監督賞、最優秀脚本賞、最優秀主演男優賞(緒形拳)、最優秀主演女優賞(いしだあゆみ)、最優秀助演女優賞(原田美枝子)など主要部門を独占。 |
| 第60回 キネマ旬報ベスト・テン | 日本映画第5位、読者選出日本映画第1位、助演女優賞(いしだあゆみ) |
| 第29回 ブルーリボン賞 | 主演女優賞(いしだあゆみ) |
| 第11回 報知映画賞 | 主演女優賞(いしだあゆみ)、助演女優賞(原田美枝子) |
映画やドラマのキャストは?
『火宅の人』は、これまでにテレビドラマと映画で映像化されています。どちらも豪華なキャストが揃い、大きな話題となりました。
1979年 テレビドラマ版(日本テレビ)
日本テレビ系の「火曜劇場」枠で放送されました。ベテラン俳優たちが重厚な人間ドラマを繰り広げました。
- 桂一雄 役:三國連太郎
- 桂ヨリ子 役:池内淳子
- 矢島恵子 役:原田美枝子
1986年 映画版(東映)
深作欣二監督がメガホンを取り、日本アカデミー賞を総なめにした傑作です。俳優たちの鬼気迫る演技が大きな見どころとなっています。
| 役名 | 俳優名 | 役どころ |
|---|---|---|
| 桂一雄 | 緒形拳 | 主人公。破滅的な生き様を体現。 |
| ヨリ子 | いしだあゆみ | 耐え忍ぶ妻。数々の女優賞を受賞。 |
| 矢島恵子 | 原田美枝子 | 激しい気性の愛人。ドラマ版に続き同役を演じた。 |
| 葉子 | 松坂慶子 | 放浪中に出会う女。原作にはない映画版オリジナルの見せ場が多い。 |
| 中原中也 | 真田広之 | 一雄の回想シーンに登場する詩人。 |
| 太宰治 | 岡田裕介 | 一雄の旧友である作家。 |
特に映画版は、緒形拳といしだあゆみの壮絶な夫婦喧嘩のシーンや、松坂慶子との濡れ場などが伝説として語り継がれています。小説を読んだ後に映像作品を観ることで、また違った感動を味わえるかもしれません。
読者の感想やレビューを紹介

『火宅の人』は、その壮絶な内容から、読者によって評価が大きく分かれる作品です。ここでは、様々な視点からの感想やレビューを紹介します。
肯定的な意見
- 「主人公の身勝手さには腹が立つが、それを凌駕する文章の力と美しさに引き込まれた」
- 「人間の弱さやどうしようもなさが赤裸々に描かれていて、共感はできなくても心に突き刺さるものがあった」
- 「特に料理の描写が素晴らしく、主人公の生きるエネルギーを感じた」
- 「家族とは、愛とは何かを考えさせられる、重厚な読書体験だった」
否定的な・複雑な意見
- 「ただの自己中心的な男性の不倫物語で、全く共感できなかった」
- 「家族、特に子供たちが不憫で、読んでいて辛くなった」
- 「昭和の作家の豪快さを美化しすぎているように感じた」
このように、主人公の生き方に対する賛否は分かれますが、多くの読者が檀一雄の卓越した文章力や、人間の本質をえぐるような洞察力を高く評価していることがわかります。好き嫌いはあるかもしれませんが、一度は読んでみる価値のある文学作品と言えるでしょう。
どこで読める?青空文庫にある?
『火宅の人』を読んでみたいと思った場合、どこで手に入れることができるのでしょうか。
書籍での購読
現在、最も手に入りやすいのは新潮文庫から刊行されている上下巻です。全国の書店や、Amazonなどのオンラインストアで手軽に購入できます。2003年に改版されており、読みやすい形で現在も流通しています。
- 火宅の人 (上) (新潮文庫)
- 火宅の人 (下) (新潮文庫)
まずはこの文庫版を探してみるのがおすすめです。
青空文庫での公開は?
残念ながら、2025年現在、『火宅の人』は青空文庫では公開されていません。
青空文庫は、著作権が消滅した作品などを公開する電子図書館です。日本の著作権法では、著者の死後70年まで著作権が保護されます。檀一雄は1976年に亡くなったため、彼の作品の著作権保護期間はまだ満了していません。そのため、合法的に無料で読むことはできない状況です。
作品を読むには、書店や図書館を利用する必要があります。
「火宅の人」小説のあらすじについて総括
この記事では、檀一雄の不朽の名作『火宅の人』について、あらすじから背景まで詳しく解説しました。最後に、記事の要点をリストで振り返ります。
- 「火宅の人」は作家・檀一雄の遺作である長編私小説
- 主人公の桂一雄は妻子がありながら愛人と暮らす
- 物語は家庭の崩壊と再生、人間の業を描く
- タイトルの「火宅」は苦悩に満ちた現世を指す仏教用語
- 主人公のモデルは作者の檀一雄自身
- 愛人・恵子のモデルは女優の入江杏子
- ただし内容は完全な事実ではなく創作も含まれる
- 読売文学賞や日本文学大賞など数々の賞を受賞
- 1979年に三國連太郎主演でテレビドラマ化
- 1986年に緒形拳主演、深作欣二監督で映画化
- 映画版は日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞
- 読者からは賛否両論あるが文章力を評価する声が多い
- 作者の檀一雄は「最後の無頼派」と呼ばれる作家
- 作品は新潮文庫から上下巻で刊行されている
- 著作権保護期間中のため青空文庫では読めない