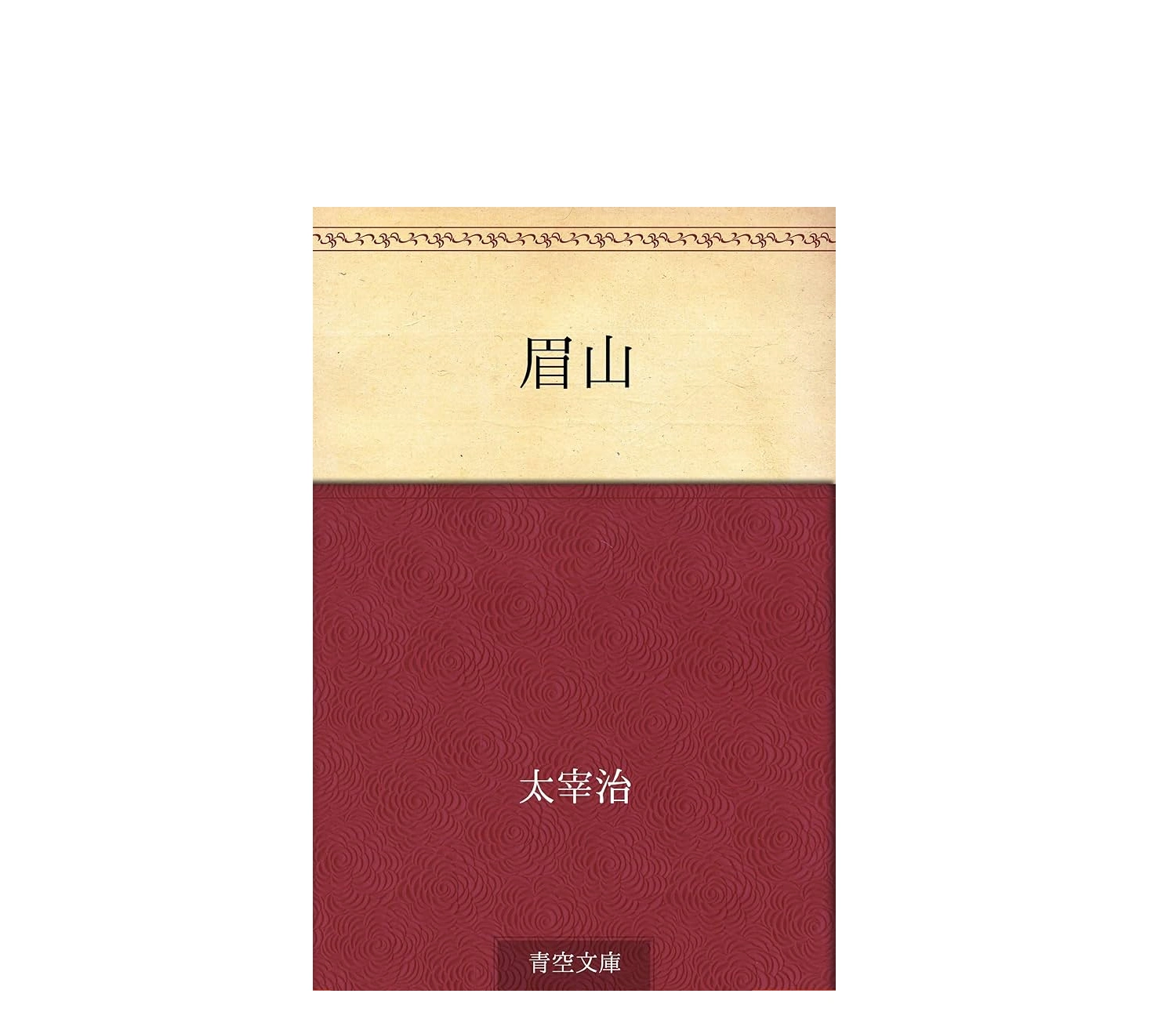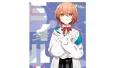太宰治の小説『眉山』のあらすじについて詳しく知りたいと思っていませんか?戦後の新宿を舞台にしたこの短編小説は、その衝撃的な結末から多くの読者に強烈な印象を残しています。この記事では、『眉山』の詳しいあらすじはもちろん、物語を彩る登場人物、そして物語の見どころや結末に関する深い考察まで、余すところなく解説します。
さらに、様々な読者の感想やレビュー、作者である太宰治の人生が作品に与えた影響にも触れていきます。私の感想も交えつつ、太宰治の小説「眉山」は無料で読める?といった、読者が抱く素朴な疑問にもしっかりとお答えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
- 太宰治『眉山』の結末を含む詳しいあらすじ
- 物語を深く味わうための登場人物と時代背景
- 作品のテーマに関する考察と様々な読者の感想
- 作者・太宰治の人生と作品の関連性
太宰治の小説「眉山」のあらすじを解説

- 物語の結末がわかる詳しいあらすじ
- 物語を彩る魅力的な登場人物
- 物語の転換点となる見どころと考察
- 舞台となった戦後日本の時代背景
- トシちゃんに込められた新たな女性像
物語の結末がわかる詳しいあらすじ
太宰治の『眉山』は、戦後間もない新宿の飲み屋「若松屋」を舞台にした物語です。小説家の端くれである主人公の「僕」は、つけが利くこの店に入り浸っていました。
若松屋には「トシちゃん」という二十歳前後の女中がいます。彼女は無知で図々しく、出しゃばりな性格から「僕」やその仲間たちから疎まれていました。ある日、ピアニストの川上六郎を店に連れて行った際、トシちゃんが彼を明治の文豪・川上眉山(かわかみ びざん)と勘違いしたことから、彼女は陰で「眉山」というあだ名で呼ばれるようになります。
眉山の迷惑な行動は後を絶ちません。階段をドスンドスンと乱暴に昇り降りしたり、トイレを汚して「眉山の大海」と揶揄されたり、「僕」たちが話していると頓珍漢な相槌を打って会話の腰を折ったりと、その振る舞いは常に「僕」たちを不快にさせました。特に、配給の味噌を盛大に踏みつけてしまう「ミソ踏み事件」は、彼女のそそっかしさを象徴する出来事として仲間内で笑いの種にされます。
しかし、物語の終盤、この状況は一変します。ある日、「僕」が友人の橋田氏から、眉山が若松屋を辞めたことを聞かされます。その理由は、彼女が重い腎臓結核を患っており、もう長くは生きられないという衝撃的なものでした。
物語の核心(ネタバレ注意)
これまで眉山の迷惑行為だと思われていた頻繁なトイレの使用や、階段を慌てて駆け下りる行動は、すべて病気の症状によるものだったのです。彼女は「僕」たち小説家(と彼女が思い込んでいる人々)のそばに少しでも長くいたい一心で、限界まで我慢していたのでした。
このあまりにも悲しい真実を知った「僕」は、思わず「いい子でしたがね。」と呟きます。そして、これまで眉山を疎んじ、陰で嘲笑っていた自分たちの言動を思い返し、地団駄を踏みたいほどの激しい後悔と自己嫌悪に苛まれます。結局、「僕」たちは眉山の思い出が詰まった若松屋で飲むことができなくなり、その日を境にぱったりと足を運ばなくなってしまうのでした。
物語を彩る魅力的な登場人物
『眉山』の物語は、個性豊かな登場人物たちのやり取りによって進行します。ここでは、物語を理解する上で欠かせない主要な人物を紹介します。
| 登場人物 | 概要 |
|---|---|
| 僕 | 物語の語り手。小説家の端くれで、若松屋の常連。トシちゃんのことを疎ましく思い、仲間たちと陰口を叩く。 |
| トシちゃん(眉山) | 若松屋の女中。二十歳前後。小説が好きだが知識は浅く、無知で図々しい振る舞いから「眉山」とあだ名をつけられる。 |
| 橋田新一郎 | 「僕」の友人である洋画家。若松屋では「林芙美子先生」ということになっている。物語の最後にトシちゃんの真実を「僕」に伝える。 |
| おかみさん | 若松屋の女主人。トシちゃんの体調を心配し、病院へ連れて行く。 |
僕(主人公)
小説家としての自分に一種のプライドを持ちながらも、つけが利くという理由で若松屋に入り浸る、どこか人間臭い人物です。仲間たちと集まっては、トシちゃんの無知や無作法を笑いものにしますが、その根底には知識人としての傲慢さが垣間見えます。しかし、物語の最後に彼女の真実を知ったとき、自身の軽薄さを恥じ、深い後悔の念に駆られることになります。
トシちゃん(眉山)
本作のキーパーソンです。背が低く色黒で、顔はひらべったいと容姿は褒められませんが、眉だけは美しい三日月型をしています。彼女の言動は一見すると、無知で空気が読めない迷惑な存在に映ります。しかし、その行動の裏には、重い病と闘いながらも、憧れの(と彼女が信じている)小説家たちに懸命に尽くそうとする、健気で純粋な心が隠されていました。
物語の転換点となる見どころと考察

『眉山』の最大の魅力は、物語の終盤で明かされる衝撃の事実によって、それまでの物語の印象が180度覆される点にあります。ここでは、物語の見どころとテーマについて考察します。
ユーモラスな前半と悲劇的な後半の対比
物語の前半は、トシちゃんの頓珍漢な言動や「ミソ踏み事件」など、軽快でユーモラスな筆致で描かれています。読者は「僕」と同じ視点でトシちゃんを「困った子だな」と微笑ましく、あるいは軽蔑的に見てしまうでしょう。しかし、後半で彼女の病気が発覚した瞬間、それまでの笑いは一転して、痛切な悲しみと後悔に変わります。この鮮やかな転換こそが、本作の最大の見どころです。
「いい子でしたがね」に込められた意味
考察のポイント
物語の結びで「僕」が漏らす「いい子でしたがね。」という一言。これは単なる同情の言葉ではありません。この言葉には、彼女の真の姿を何一つ理解しようとせず、表面的な言動だけで彼女を判断し、嘲笑していた自分自身への痛烈な自己嫌悪と、もはや取り返しのつかない過去への深い悔恨が凝縮されています。
私たちは日常生活において、他人の一部分だけを見て、その人の全てを分かった気になってしまうことがあります。『眉山』は、そうした人間の浅はかさや傲慢さを鋭く突きつけ、読者自身の胸に深く突き刺さる問いを投げかけてくるのです。
舞台となった戦後日本の時代背景
『眉山』を深く理解するためには、物語が描かれた時代背景を知ることが重要です。
物語の冒頭には、「これは、れいの飲食店閉鎖の命令が、未だ発せられない前のお話である。」という一文があります。これは、食糧難を背景に1947年(昭和22年)に発令された「飲食営業緊急措置令」を指しています。つまり、物語の舞台は第二次世界大戦の敗戦から間もない、1945年後半から1947年初頭にかけての東京・新宿です。
復興期の新宿
東京大空襲で焼け野原となった新宿ですが、物語にあるように「最も早く復興したのは、飲み食いをする家であった」とされています。若松屋のような急ごしらえの飲食店が次々と建ち、人々がたくましく生きようとしていた、そんな混乱と活気が入り混じった時代でした。
このような時代背景は、登場人物たちの刹那的な生き方や、先の見えない不安感を物語に与えています。「僕」たちが若松屋で夜通し酒を飲む姿は、厳しい現実から一時的に逃避しようとする当時の人々の心情を映し出しているとも考えられるでしょう。
トシちゃんに込められた新たな女性像

太宰治は、女中のトシちゃんという人物を通して、何を伝えたかったのでしょうか。
当時の「女中」は、現代の家政婦とは異なり、比較的低い身分と見なされ、十分な教育を受けられない女性が就くことの多い職業でした。作中でも「僕」たちは彼女の無知を嘲笑の対象としています。
しかし、彼女は「小説というものがメシよりも好きだった」と語り、決して裕福とは言えない状況で文芸雑誌を買い求めるなど、知的なものへの純粋な憧れを持っています。これは、戦前の「女性に学問は不要」といった風潮からの脱却を象徴していると捉えることができます。
太宰は、身分や性別に関係なく、誰もが文学を愛し、自由に自己表現できる新しい時代への希望を、健気で純粋なトシちゃんの姿に託したのかもしれません。彼女の悲劇的な結末は、その希望がまだ脆く、儚いものであったことを示唆しているようにも思えます。
小説「眉山」のあらすじ以外の太宰治の世界

- 作品に対する様々な読者の感想・レビュー
- 管理人おうみである私の感想
- 作者・太宰治の人生と作品の関係性
- 太宰治の小説「眉山」は無料で読める?
- 結論:太宰治の小説「眉山」あらすじと魅力
作品に対する様々な読者の感想・レビュー

『眉山』は多くの読者の心を揺さぶり、様々な感想が寄せられています。ここでは、代表的なレビューをいくつか紹介します。
読後感がすごい…
前半のコミカルな雰囲気から一転、最後の数ページで突き落とされる感覚。読み終わった後、しばらく動けなくなりました。太宰治のすごさを改めて感じさせられる傑作短編です。
自己嫌悪に陥る
トシちゃんを笑っていた「僕」たちに腹を立てていたのに、気づけば自分も同じように彼女を見ていたことに気づかされました。人の一面だけを見て判断してはいけないと、深く反省させられます。
涙なしには読めない
彼女の全ての行動が、病気のせいであり、そして「僕」たちへの奉仕の心からだったと知った時、涙が止まりませんでした。切なくて、苦しい。でも、読む価値のある物語です。
このように、多くの読者が物語前半と後半のギャップに衝撃を受け、登場人物たちへの、そして自分自身への「自己嫌悪」や「後悔」の念を抱いていることがわかります。この強烈な読後感こそが、『眉山』が時代を超えて読み継がれる理由の一つと言えるでしょう。
管理人おうみである私の感想
私自身、この『眉山』という作品を初めて読んだときの衝撃は今でも忘れられません。
この物語の核心は、「真実は、見えているものとは限らない」という普遍的なテーマにあると感じています。私たちは、トシちゃんの表面的な「無知」や「無作法」という情報だけで彼女を判断してしまいます。しかし、その内側には病という、他者からは窺い知れない「真実」が隠されていました。
これは、現代社会に生きる私たちにとっても非常に示唆に富んでいます。SNSなどで他人の断片的な情報に触れ、簡単にその人物を評価し、時には批判してしまうことがあります。しかし、その背景にある事情や苦悩を私たちはどれだけ想像できているでしょうか。
太宰治は『眉山』を通して、表面的な情報だけで他者を断罪することの危うさと、見えない部分を想像する思いやりの重要性を、私たちに教えてくれているように思います。この物語は、単なる悲しい話ではなく、人間関係における大切な教訓を与えてくれる、深い作品です。
作者・太宰治の人生と作品の関係性
『眉山』が発表されたのは1948年(昭和23年)3月。これは、太宰が山崎富栄と入水自殺するわずか3ヶ月前のことです。彼の晩年の心境が、この作品に色濃く反映されていると考えられます。
太宰治自身、生涯を通じて結核などの病に苦しみ、薬物中毒や度重なる自殺未遂を繰り返しました。彼は、常に「人間失格」という意識、つまり他者から理解されない孤独感や罪悪感を抱えていたと言われています。
この作品における「僕」の、トシちゃんの真実を知った後の激しい後悔と自己嫌悪は、太宰自身が人生で感じてきた悔恨の念と重なる部分があるのかもしれません。人を傷つけ、そして自分も傷ついてきた太宰だからこそ、このような人間の内面をえぐるような物語を描くことができたのではないでしょうか。
晩年の名作との関連
『眉山』は、同じ時期に執筆された『斜陽』や『人間失格』といった代表作ともテーマ的に通底しています。他者とのすれ違い、分かり合えないことの悲しさ、そして救いのない現実といった太宰文学のエッセンスが、この短い物語の中に凝縮されているのです。
太宰治の小説「眉山」は無料で読める?

結論から言うと、はい、太宰治の『眉山』はインターネット上で無料で読むことができます。
その理由は、日本の著作権法に関係しています。作者の死後、一定の期間が経過すると著作権が消滅し、その作品は「パブリックドメイン(社会の共有財産)」となります。太宰治は1948年に亡くなっているため、彼のほとんどの作品は著作権保護期間が満了しています。
「青空文庫」で読もう!
無料で日本の文学作品を公開している電子図書館サービス「青空文庫」では、『眉山』をはじめとする太宰治の多くの作品を読むことが可能です。パソコンやスマートフォン、タブレットからいつでも手軽にアクセスできます。
わざわざ本を購入しなくても、気軽に名作に触れることができるのは嬉しいポイントです。ぜひ一度、原文を読んでみることをおすすめします。
結論:太宰治の小説「眉山」あらすじと魅力
この記事では、太宰治の短編小説『眉山』について、あらすじから考察、読者の感想まで幅広く解説しました。最後に、本記事の要点をまとめます。
- 『眉山』は戦後間もない新宿の飲み屋を舞台にした物語
- 主人公の「僕」は女中のトシちゃんを無知で迷惑な存在だと思っている
- トシちゃんは勘違いから「眉山」というあだ名で呼ばれる
- 物語の前半は眉山の迷惑行為がユーモラスに描かれる
- しかし物語の終盤、眉山が重い腎臓結核であることが発覚する
- 彼女の行動はすべて病気の症状と奉仕の心によるものだった
- 真実を知った「僕」は激しい後悔と自己嫌悪に苛まれる
- 「いい子でしたがね」というセリフに登場人物の後悔が凝縮されている
- 本作の魅力は、物語の印象が180度覆る衝撃的な結末にある
- 人間の表面的な理解の危うさという普遍的なテーマを描いている
- 舞台となった戦後の混乱期が物語に深みを与えている
- 作者である太宰治自身の晩年の心境が色濃く反映された作品
- 多くの読者が強烈な読後感と自己嫌悪を感じると評価している
- 著作権保護期間が満了しているため無料で読むことが可能
- 電子図書館サービス「青空文庫」で手軽に作品に触れられる