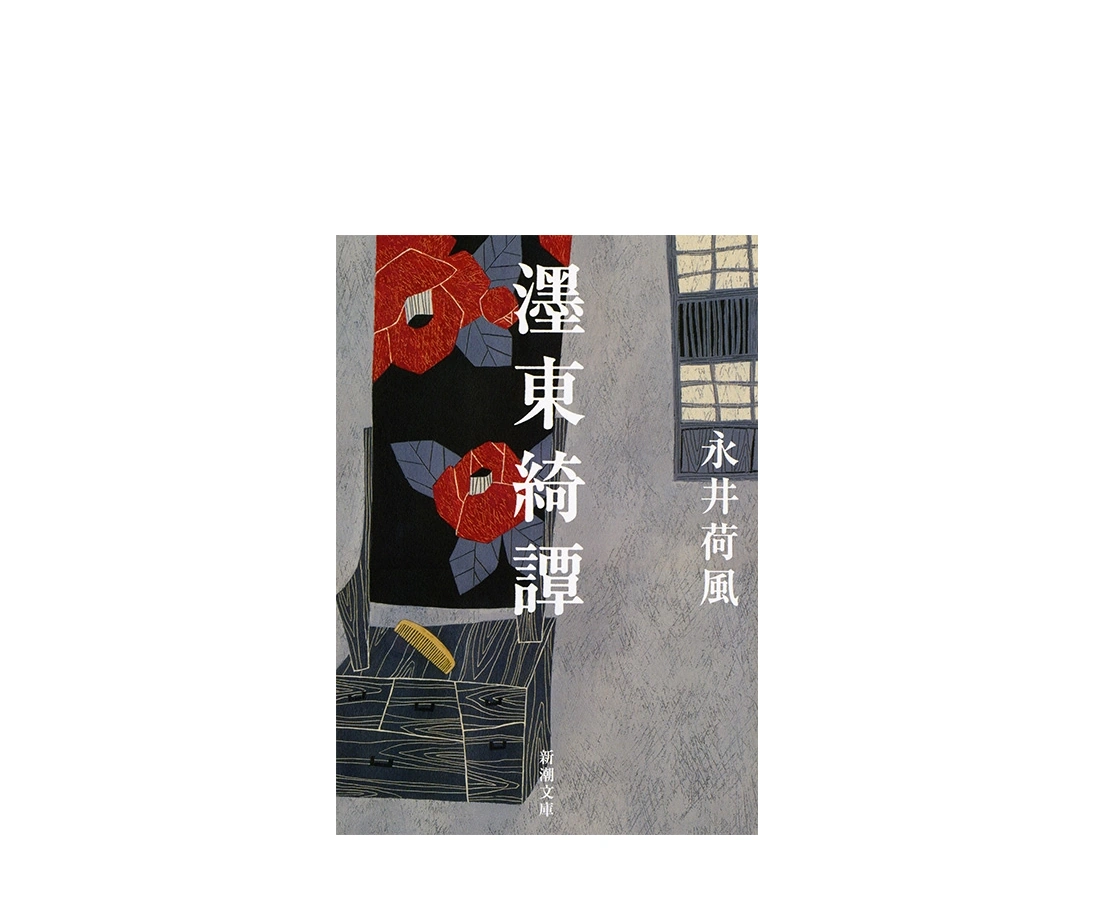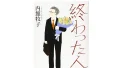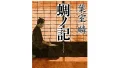永井荷風の不朽の名作『濹東綺譚』。その小説のあらすじを詳しく知りたいと思っていませんか?
この記事では、物語の核心であるあらすじはもちろん、タイトルの「濹東綺譚」が持つ意味や、魅力的な登場人物であるお雪についての詳細な解説をお届けします。さらに、作者・永井荷風の人物像、実際にこの作品を読んだ人々の感想、そして1960年版や2010年版を含む映画化に関する情報まで、幅広く網羅しました。
「どこで読めるの?」「青空文庫にはある?」といった具体的な疑問にもお答えし、この物語が持つ独特の空気感と奥深い魅力を、余すところなくお伝えします。
- 濹東綺譚のあらすじと登場人物がわかる
- 作者・永井荷風と作品の時代背景を理解できる
- 映画や挿絵など小説以外の楽しみ方が見つかる
- 作品に関する読者の様々な感想や評価を知れる
濹東綺譚の小説あらすじと作品の基本情報

- 小説のあらすじをわかりやすく紹介
- 主要な登場人物であるお雪の人物像
- 作品の世界観がわかる詳細な解説
- 作者である永井荷風はどんな人物か
小説のあらすじをわかりやすく紹介
『濹東綺譚』の物語は、50代後半の小説家・大江匡(おおえ ただす)が、執筆中の小説『失踪』の構想を練るために、東京の向島・玉の井周辺を散策するところから始まります。
6月の末、梅雨の晴れ間に散策していた大江は、突然の激しい夕立に見舞われます。傘を広げたそのとき、「檀那、そこまで入れてってよ」と声をかけられ、一人の女性が傘の中に飛び込んできました。それが私娼として働く26歳の女性、お雪でした。
この運命的な出会いをきっかけに、大江はお雪のもとへ足しげく通うようになります。二人は客と娼婦という関係を超えて、次第に心を通わせていきます。大江は自分の職業を曖昧にし、お雪は大江を秘密出版に関わる人物ではないかと誤解したまま、二人の間には穏やかで親密な時間が流れます。
しかし、ある日お雪は「借金を返済したら、おかみさんにしてくれないか」と大江に想いを打ち明けます。過去に女性を家庭に入れて失敗した経験を持つ大江は、自分がお雪を本当の意味で幸せにすることはできないと考え、静かに彼女のもとを去る決意を固めます。
秋が深まり、大江の足は玉の井から遠のいていきました。後日、お雪が入院したことを人づてに聞きますが、二人が再会することはありません。互いの本名すら知らないまま始まった淡い恋は、季節の移ろいとともに、はかなく終わりを告げるのです。
主要な登場人物であるお雪の人物像

この物語のヒロインであるお雪は、玉の井の私娼窟で働く26歳の女性です。かつては宇都宮で芸者をしていたという過去を持ちます。
彼女の魅力は、その素朴で純真な性質にあります。私娼という過酷な境遇にありながらも、その心はすれておらず、作中では健康的な容貌と曇りのない黒目がちな瞳が印象的に描かれています。
お雪のモデル
お雪のモデルは、作者である永井荷風の日記『断腸亭日乗』に登場する女性だと考えられています。荷風は実際に玉の井に通い、特定の女性と親しくなりました。そのときの体験が、お雪という人物像に色濃く反映されているのです。
物語の中で、お雪は大江を「秘密出版に関わる男」と誤解しますが、そのことを深く詮索せず、ただ彼との時間を慈しみます。そして、借金を返済した暁には「おかみさんにしてほしい」と、ささやかな未来の夢を打ち明ける純粋さを持っています。
このようにお雪は、社会の底辺で生きながらも人間らしい温かさや純情さを失わない、滅びゆく江戸情緒を体現したかのような女性として描かれており、多くの読者を惹きつけてやみません。
作品の世界観がわかる詳細な解説

『濹東綺譚』を深く理解するためには、その独特の世界観と構造を知ることが重要です。
舞台となった「玉の井」
物語の舞台である玉の井は、現在の東京都墨田区東向島にあった私娼窟です。関東大震災後、浅草から移転してきた銘酒屋が集まり、迷路のように入り組んだ路地に「抜けられます」という看板が立つ、独特の雰囲気を醸し出す街でした。
荷風は、近代化していく東京の中で、あえて時代から取り残されたようなこの場所に強く惹かれました。どぶの匂いや蚊の羽音といった猥雑な空気の中に、むしろ失われつつある江戸の情緒や人間味を見出していたのです。
入れ子構造(メタフィクション)
この小説は、単純な恋愛物語ではありません。主人公の大江が『失踪』という別の小説を書いている、という「入れ子構造」になっています。
読者は、大江がお雪と出会い、関係を深めていく現実の物語と、その体験が反映されていく作中作『失踪』の物語を同時に追体験することになります。この手法により、物語に奥行きが生まれ、作者・荷風自身の創作過程を覗き見るような感覚を味わうことができるのです。
『濹東綺譚』の世界観のポイント
- 舞台:近代化から取り残された私娼窟・玉の井
- 構造:主人公が小説を書く「入れ子構造」
- テーマ:滅びゆく江戸情緒への哀惜と、時代への反発
作品が執筆された昭和11年(1936年)は、二・二六事件が起こるなど軍国主義の足音が日増しに高まっていた時代です。荷風はそうした世相に背を向け、玉の井という別世界に安らぎと創作のインスピレーションを求めたと考えられます。
作者である永井荷風はどんな人物か
『濹東綺譚』の作者である永井荷風(ながい かふう)は、1879年から1959年までを生きた、近代日本を代表する小説家の一人です。
高級官僚の家庭に生まれましたが、厳格な家風に反発し、若くして文学の道を志します。父の意向でアメリカやフランスへ遊学しますが、実業には全く興味を示さず、むしろ西洋の文化や芸術に深く傾倒しました。その経験は『あめりか物語』や『ふらんす物語』といった作品に結実し、文壇での地位を確立します。
荷風は、生涯を通じて文壇の権威や流行を嫌い、アカデミズムとも距離を置く孤高の存在でした。その一方で、市井の人々や花柳界に生きる女性たちに眼差しを向け、粋(いき)や江戸文化の美意識を生涯にわたって追求したのです。
彼のライフワークともいえるのが、30年以上にわたって書き続けられた日記『断腸亭日乗(だんちょうていにちじょう)』です。ここには、日々の散策の記録、カフェーや遊郭通いの様子、そして『濹東綺譚』をはじめとする作品の創作過程が詳細に記されており、当時の風俗を知る上でも貴重な資料となっています。
このように永井荷風は、近代化・西洋化する日本社会に批判的な目を向け、失われゆく江戸の情緒をこよなく愛し、それを独自の美学で作品に昇華させた作家だったといえるでしょう。
小説「濹東綺譚」のあらすじ以外の楽しみ方

- 濹東綺譚というタイトルの意味とは?
- 作品の評価を高めた木村荘八の挿絵
- 読者の感想から見る作品の評価
- 映画化された1960年版と2010年版
- どこで読める?青空文庫や文庫本情報
- 濹東綺譚の小説あらすじと魅力の総括
濹東綺譚というタイトルの意味とは?

『濹東綺譚』という特徴的なタイトルには、深い意味が込められています。
まず「墨東(ぼくとう)」とは、隅田川の東岸地域を指す言葉です。物語の舞台である玉の井(現在の墨田区)がこの地域にあることから名付けられました。そして「綺譚(きたん)」は、美しくも不思議な物語、という意味を持ちます。
つまり、タイトル全体で「隅田川の東岸で繰り広げられた、美しくも不思議な物語」を表現しているのです。
本来の漢字の秘密
最も特徴的なのが、本来のタイトルで使われている冒頭の漢字です。この字は、さんずい(氵)に「墨」を組み合わせたもので、一般的には使われない荷風の造詣の深さを示しています。
もともとは江戸時代の儒学者・林述斎(はやし じゅっさい)が作った字で、隅田川の別称である「墨水(ぼくすい)」や「墨田川」を表すために考案されました。荷風はこの珍しい字を見つけ出し、自作のタイトルに用いることで、作品に江戸の香りや知的な遊び心を添えたのです。
現在では、この特殊な漢字を表示できない環境も多いため、本記事でも一般的な表記である『濹東綺譚』に統一しています。
作品の評価を高めた木村荘八の挿絵
『濹東綺譚』の魅力を語る上で、画家・木村荘八(きむら しょうはち)による挿絵の存在は欠かせません。
この作品が1937年に新聞連載された際、挿絵を担当したのが木村荘八でした。彼は挿絵の依頼を受けると、連日のように玉の井界隈へ足を運び、その湿った空気感や迷路のような路地の風情を丹念に写し取りました。
彼の描く挿絵は、単なる文章の補足にとどまりません。例えば、大江とお雪が夕立の中で出会う有名な場面の挿絵は、雨の匂いや町のざわめきまでもが伝わってくるような詩情にあふれています。
荷風の文と荘八の絵の関係
この二人の共作は、しばしば日本の伝統芸能である「義太夫」における、物語を語る太夫(たゆう)と、情景を音で表現する三味線弾きの関係に例えられます。文章と絵が互いに高め合い、一体となって作品の世界観を創り上げているのです。
現在でも、岩波文庫版の『濹東綺譚』には木村荘八の挿絵が全て収録されており、文章と共に味わうことで、より深く物語の世界に浸ることができます。この挿絵があったからこそ、『濹東綺譚』は不朽の名作としての評価を不動のものにした、という意見も少なくありません。
読者の感想から見る作品の評価

『濹東綺譚』は発表から長い年月が経った今でも、多くの読者に愛され、様々な感想が寄せられています。
肯定的な感想
多くの読者が称賛するのは、やはりその美しい文章と情緒あふれる雰囲気です。特に、季節の移ろいや光、音、匂いなどを繊細に捉えた描写は高く評価されています。
- 「黄昏時に読むと、作品の世界に引き込まれる」
- 「情景描写が巧みで、当時の玉の井の空気が伝わってくる」
- 「明確な結末がないからこそ、読後に深い余韻が残る」
また、主人公の大江が直接的な行動を起こさず、あくまで「傍観者」としてお雪や街を眺めている点に、独特の美学を感じるという声もあります。
様々な視点からの感想
一方で、そのテーマ性から、読者の立場によって様々な意見が見られます。
特に女性の読者からは、「私娼を題材にしている点で、女性を蔑んでいるように感じる」といった厳しい意見が出されることもあります。これに対し、男性の読者からは「これは女性蔑視ではなく、むしろ滅びゆくものへの愛惜を込めた女性賛美だ」と反論されるなど、ジェンダーの観点から活発な議論を呼ぶ作品でもあります。
「小説なのか随筆なのかわからない、不思議な作品」「思想性がなく、ただ美しいだけ」といった感想もあり、その捉えどころのなさが、かえってこの作品の奥深さにつながっているのかもしれません。
映画化された1960年版と2010年版
『濹東綺譚』は、その魅力から幾度となく映像化されています。ここでは主要な3作品を比較して紹介します。
| 公開年 | 監督 | 主演(大江役 / お雪役) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1960年 | 豊田四郎 | 芥川比呂志 / 山本富士子 | 芸術祭参加作品。原作の雰囲気を忠実に再現した文芸映画の傑作と名高い。主人公の名は「種田順平」に変更されている。 |
| 1992年 | 新藤兼人 | 津川雅彦 / 墨田ユキ | 荷風自身の半生を重ね合わせ、より作家の内面に迫る。東京大空襲で二人が別れるという独自の結末が描かれた。 |
| 2010年 | 荒木太郎 | 那波隆史 / 早乙女ルイ | ピンク映画として製作。舞台を現代の上野に移し、原作を大胆に翻案している。R-18指定。 |
1960年の豊田四郎監督版は、お雪を演じた大女優・山本富士子の美しさが際立ち、原作の詩的な情緒を見事に映像化したと評価されています。
1992年の新藤兼人監督版は、津川雅彦が円熟の演技で荷風自身を体現し、戦争という大きな時代のうねりの中に物語を位置づけた意欲作です。
このように、監督や時代によって解釈が異なり、それぞれの作品を見比べることで、『濹東綺譚』という物語が持つ多面的な魅力をより深く発見することができます。
どこで読める?青空文庫や文庫本情報
『濹東綺譚』を読んでみたいと思った場合、いくつかの方法で手に入れることができます。
文庫本で読む
現在、主に以下の出版社の文庫本が流通しており、書店やオンラインストアで容易に入手可能です。
- 岩波文庫版:木村荘八の挿絵が全て収録されており、作品の世界観を余すところなく味わいたい方におすすめです。
- 新潮文庫版:改版も重ねられており、手に取りやすい一冊です。解説も充実しています。
- 角川文庫版:こちらも広く普及している定番の文庫本です。
安岡章太郎『私の濹東綺譚』もおすすめ
中公文庫からは、作家・安岡章太郎のエッセイ『私の濹東綺譚』に、小説本編が併録された形で刊行されています。同時代を生きた作家の視点から作品を読み解くエッセイは、物語をより深く理解する助けとなるでしょう。
青空文庫で読めるか?
2025年現在、永井荷風の『濹東綺譚』は青空文庫で無料で読むことができます。
もちろん、紙の本でじっくりと世界観に浸りたい方や、前述した木村荘八の美しい挿絵と共に楽しみたい方は、各社から出版されている文庫本を手に取るのもおすすめです。
濹東綺譚の小説あらすじと魅力の総括
この記事で解説してきた、永井荷風『濹東綺譚』の小説あらすじと作品の魅力について、最後に要点をまとめます。
- 『濹東綺譚』は永井荷風の最高傑作とされる小説
- 舞台は東京・玉の井の私娼窟
- 小説家の大江匡と娼婦お雪の出会いと別れを描く物語
- 主人公の大江は作者・永井荷風の分身と考えられる
- 夕立の中の出会いのシーンは特に有名で詩情的
- お雪は純朴な性質を持つ26歳の女性
- 大江はお雪からの求愛を受け入れず静かに去っていく
- 明確な結末を描かない余韻のある終わり方が特徴
- タイトルは「隅田川東岸の物語」を意味する
- 本来のタイトルには特殊な漢字が使われている
- 木村荘八による挿絵が作品の評価を大きく高めている
- 小説と挿絵は「義太夫」の関係に例えられる
- 感想は「名文」という賛辞から「女性蔑視」という批判まで多様
- 1960年、1992年、2010年などに映画化されている
- 現在、青空文庫で読むことはできない